御香宮神社(ごこうのみやじんじゃ)は、安産・子育てのご利益で有名な「神功皇后(じんぐうこうごう)」がお祀りされています。
桃山文化の香りが残る絢爛豪華な本殿や拝殿。名水百選「御香水」、小堀遠州ゆかりの庭園など見どころも多数。
なぜ神功皇后が安産の神さま? 平安時代に御香水が湧き出たと伝わりますが、社殿は桃山文化。その理由は?
ご利益・由緒・見どころやアクセスをまとめました。
タップできる|目次|
【1】安産の社 御香宮神社
御祭神・神功皇后の霊験神話から、安産・子育ての御利益で信仰されています。
・祭神
- 主祭神:神功皇后
- 相殿神:応神天皇、仲哀天皇、ほか六神を祀っています。
・神功皇后の神話
神功皇后は、第14代天皇、仲哀天皇 [在位192-200年] の皇后。
神と交感する能力を持つ巫女的な女性だったようです。
古事記|神功皇后のミラクルな神話
神功皇后の夫、仲哀天皇は「海のかなたの宝の国を授けよう」と神託を受けましたが、信じなかったため神の怒りに触れて亡くなります。そして‥
- 神功皇后は臨月を迎えていましたが、神託に従い朝鮮半島の新羅に向かいます。海を渡る時、大小の魚が寄り集まって船の進行を助けつつ、追い風が舟を進めたといいます。
そして、お腹に石を当ててさらしで巻き、冷やすことによって出産を遅らせたといいます。 - そんな神功皇后の勢いに新羅の国王は恐れおののき、降伏して朝貢することを誓い、後に高句麗・百済もこれに従いました。(三韓征伐)
- 帰国後、筑紫で凱旋してから応神天皇(八幡神)を無事に出産。
- 大和に戻り、他の王らの反逆の企ても粉砕、御子を皇太子に立てて、摂政として約70年間みずから政治をとったといわれています。 [在位201-269年]
※記紀の記載上、皇后は皇位に就かなかったことになっていますが、天皇に匹敵する存在であり、日本書紀でも天皇に準じた扱いをしています。

神功皇后が出産を遅らせるために使った石は「月延石(つきのべいし)」と呼ばれます。
その石は3つあり、長崎県の「月讀神社」、京都市の「月読神社」、福岡県の「鎮懐石八幡宮」に奉納されたと伝わります。
筑紫(福岡)の地に実在を伝えられる鎮めの石は、「鎮懐石」の名で8世紀初頭の歌人山上憶良の歌に、具体的な寸法と共に人々が盛んに参っていた様子が描かれています。

遥か昔の日本に、神功皇后のようなパワフルな女性がいたとは素晴らしいです!ぜひあやかりたいものですね!
【2】安産祈願、お守り
安産の社と言われる御香宮神社。安産関連の授与品が充実しています。
・安産祈願
安産・子育て・家内安全にかかわるご祈祷を受けられます。
・安産祈願ご祈祷 8,000円
・安産祈願ご祈祷(岩田帯付き)10,000円
・安産祈願ご祈祷(コルセット付き)12,000円
・初宮参り(誕生1ヶ月目)8,000円
・初誕生参り(誕生1年目)5,000円
・七五三参り 5,000円
・十三参り 5,000円
・その他、新車清祓い、厄除け、家内安全祈願のご祈祷もあります。
御祈祷受付 9:00~15:30 ※予約不要
※大安・土日祝日、これらが重なる戌の日は混雑し、複数組での御案内となる場合や1時間以上の待ち時間が発生する場合もあるそうです。時間に余裕をもって伺いましょう。
・お守り
安産のお守りが充実!プレゼントに最適な桐箱入りの安産お守りもあります。
その他、子授け、幸せ守、開運・厄除け、旅行安全、学業など。


桐箱に入ったピンクの安産御守りはプレゼントにぴったり!
【3】御香宮神社の歴史
創建年は不詳。
初めは「御諸神社(みもろじんじゃ)」と称しましたが、平安時代に香りの良い水が湧きだしたことから「御香宮」という名を天皇から賜り、現在に至ります。
・平安時代に御香水が湧き出す
平安時代の貞観4年(862年)社殿を修造。伝承によると同年、境内より良い香りの水が湧き出し、時の清和天皇から「御香宮」の名を賜ったといいます。
・華麗な桃山文化の時代
天正18年(1590年)豊臣秀吉が朝鮮出兵の戦勝を祈願し、願文と金熨斗付太刀(きんのしつきたち/重要文化財/東京国立博物館に委託)を献じました。神功皇后の朝鮮征伐にあやかるためであったといわれます。
日本の天下統一を果たした豊臣秀吉の次のターゲットは朝鮮。戦勝祈願をする際に安産祈願もしていたかもしれませんね? 1589年 鶴松、1593年 秀頼誕生。
豊臣秀吉は朝鮮出兵を始めた後、1592年に伏見城築城を開始。伏見城の鬼門除け守護神として、御香宮神社を伏見城領内に勧請し社領三百石を献じました。現在その場所は「古御香宮(ふるごこう)」と呼ばれ、御香宮神社の御旅所(おたびしょ)になっています。
そして秀吉の没後、徳川家康によって社領三百石が献じられ、元の地(現在地)に再建されました。
- 慶長10年(1605年)本殿を再建(徳川家康の寄進)
- 元和8年(1622年)表門として伏見城の大手門を移築(徳川頼房の寄進)
- 寛永2年(1625年)拝殿を建立(徳川頼宣の寄進)
・幕末維新の激動に巻き込まれ‥
明治元年(1868年)に起こった鳥羽・伏見の戦いでは、伏見町内における新政府軍(薩摩藩)の本営となり、激しい市街戦が繰り広げられましたが、本殿等は無事でした。
対する旧幕府軍は、本営 伏見奉行所に新政府軍から大砲を打ち込まれ炎上、撤退に追い込まれました。現在、伏見奉行所跡には石碑が残るのみです。
御香宮神社は、戦前までは武神として崇敬されていたそうです。実は、神功皇后は三韓征伐や、八幡神の母ということから、武神としての信仰も篤い神様なのです。

幕末の戦乱で新政府軍が勝ったので、現在も豪壮華麗な桃山文化の名残をとどめているのですね^^
【4】御香宮神社の見どころ
御香宮の名前の由来となった御香水や、桃山時代の豪華な装飾が美しい社殿、小堀遠州ゆかりの庭園など見どころ多数。
・御香水|名水百選
御香宮神社の名の由来となった清泉です。伝承によると、平安時代の貞観4年(862年)境内より良い香りの水が湧き出し、時の清和天皇から「御香宮」の名を賜ったといいます。
「石井の御香水」として、伏見の七名水の一つに数えられ、徳川頼宣、頼房、義直の各公は、この水を産湯として使われたそうです。絵馬堂には御香水の霊験説話を画題にした『社頭申曳之図』がかかっています。
明治以降、涸れていたのを昭和57年に復元し、昭和60年1月、環境庁(現、環境省)より京の名水の代表として『名水百選』に認定されました。

・本殿|豪壮華麗な装飾!
桃山時代の特色を表した豪壮華麗な大型社殿で、平成2年より着手された修理により約390年ぶりに極彩色が復元されました。(重要文化財)
建立は慶長10年(1605年)、徳川家康の命により着手。大型の五間社流造で屋根は桧皮葺(ひわだぶき)、正面の頭貫(かしらぬき)、木鼻(きばな)や蟇股(かえるまた)、向拝(こうはい)の手挟(たばさみ)には彫刻が施され極彩色に彩られています。また、背面の板面の板壁には五間全体にわたって柳と梅の絵が華やかに描かれています。
社殿修復に関する費用は、徳川三家の御寄進金を氏子一般の浄財でもって行われ、大修理時には、神主自ら江戸に下って徳川幕府直接の御寄進を仰いだ例も少なくなかったそうです。本殿には、菊の御紋(天皇と東宮)や五七の桐紋(天皇家)、葵の御紋(徳川家)が見られます。



・拝殿|豪壮華麗な装飾!
豪壮華麗な拝殿です。平成9年6月に半解体修理が竣工し極彩色が復元されました。
寛永2年(1625年)、徳川頼宣の寄進によって建立された、桁行七間(けたゆき七げん)、梁行三間(りょうゆき三げん)、入母屋造(いりもやづくり)、本瓦葺の割拝殿(わりはいでん)です。


正面軒唐破風(のきからはふ)は、手の込んだ彫刻によって埋められています。
特に五三桐の蟇股や大瓶束(たいへいづか)によって左右区切られている彫刻は、向かって右は『鯉の瀧のぼり』、すなわち龍神伝説の光景を彫刻し、左はこれに応ずる如く、琴高仙人(きんこうせんにん)が鯉に跨って瀧の中ほどまで昇っている光景を写しています。

・表門|伏見城大手門
元和8年(1622年)、徳川頼房が伏見城の大手門を拝領して寄進しました。
三間一戸、切妻造(きりもやづくり)、本瓦葺、薬医門(やくいもん)、雄大な木割、雄渾な蟇股、どっしりと落ち着いた豪壮な構えは伏見城の大手門たる貫禄を示しています。
特に注目すべきは、正面を飾る二十四孝を彫った蟇股で、向かって右から、楊香、敦巨、唐夫人、孟宗の物語の順にならんでいます。また両妻の板蟇股も非常に立派で、二十四考の彫刻と併せて桃山時代の建築装飾の代表例とされています。(重要文化財)
二十四孝(にじゅうしこう)は中国古来の教訓書。優れた孝行をした24人を取り上げた書物です。日本にも伝来し、神社仏閣等の建築物などの意匠のモチーフとしても採用されています。


・庭園|小堀遠州ゆかりの石庭
石庭拝観料:大人200円・学生150円
休館日:神社行事により、臨時休館有
拝観時間:朝9時から16時まで

小堀政一(こぼり まさかず)が元和9年(1623年)に伏見奉行に任ぜられた時に、伏見奉行所内に作った庭の石を移築して作った庭園です。現庭園の作庭は中根金作氏になります。
当時の庭園は、寛永11年(1634年)7月、上洛した三代将軍家光が立派さに感心し、遠州公に褒美として5千石を加増したほどの出来栄えだったようです。
伏見奉行所は明治時代以降、陸軍工兵隊、米軍キャンプ場と移り変わり、荒れ果て、昭和32年には市営住宅地にするため取り壊す事になりました。文化的価値の高い遠州ゆかりの庭園を残すために、当時の宮司が強く働きかけ御香宮神社に移築されました。庭園の手水鉢には、文明9年(1477)の銘があり在銘のものとしては非常に珍しいそうです。
小堀 政一(こぼり まさかず)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての大名、茶人、建築家、作庭家、書家。備中松山藩第2代藩主、のち近江小室藩初代藩主。遠州流(小堀遠州流)茶道の祖。一般には小堀 遠州(こぼり えんしゅう)の名で知られるが、「遠州」は武家官位の遠江守の唐名に由来する通称で後年の名乗り。幼名は作助、元服後は、正一、政一と改める。道号に大有宗甫、庵号に孤篷庵がある。
出典:Wikipedia
・植物|ソテツ、藤、椿
ソテツ(京都市登録天然記念物)
ソテツは南方系の裸子植物で、通常京都付近では冬期に覆いを施す必要があります。この御香宮神社のソテツは覆いなしで越冬、開花結実しており、ソテツの生育域を考えるうえで 重要な資料となっているそうです。樹齢は不明ですが、慶長十年(1605)の本殿建築時からそれほど下らない時期に植えられた可能性もあるそうです。
※開花時期7月上旬

ところがらの藤
江戸時代前期、後水尾上皇(ごみのうじょうこう)によって命名されたそうです。
遠州ゆかりの石庭に植えられています。
※開花時期4月頃
五色の散り椿(おそらく椿)
豊臣秀吉が伏見城築城の際、各地から集めた茶花の一つと伝えられます。樹齢約400年の古木。純白、ピンク、白の斑入りと五色の花が咲くそうです。小堀遠州が、これほど見事なツバキは、おそらくないだろう。と、たたえて以来「おそらく椿」とも呼ばれているそうです。特別拝観時以外は見ることができないそうです。
※開花時期3月末から4月上旬

本殿は特別拝観の時しか入れません。極彩色を見たかったので、囲いの隙間から覗きました^^
【5】御朱印、水占い
通常の御朱印とは別に、御香水をイメージさせる和紙に書かれた御朱印もあります。水占いは御香水に紙を浸けて占います。
・御朱印
御香水をイメージしたような水玉模様の和紙に書かれた書き置きの御朱印(左)と、手書きの御朱印(右)があります。

・水占い
水占いは、神功皇后が三韓征伐の折に鮎を釣り上げて戦勝を占ったという故事にちなんだものです。社務所でくじを引くことができます。
御香水に浮かべると、お告げが現れます。項目は、総運・願事・健康・金運・恋愛・旅行・色です。


水占いにある「色」の項目がちょっと面白いです^^ 桃山文化の極彩色からのアイデアかもしれないですね。
【6】御香宮神社 アクセス
最寄り駅は、近鉄京都線「桃山御陵前駅」、京阪本線「伏見桃山駅」、JR奈良線「桃山駅」。
駅から御香宮神社表門(C地点)までは、徒歩約5分です。
・京都駅から
近鉄京都線 新田辺行、橿原神宮前行、近鉄奈良行
※桃山御陵前駅まで約13分
(先頭車両に乗ると改札口が近いです)
JR奈良線 城陽行、奈良行
※桃山駅まで約13分
・祇園四条駅から
京阪本線 淀屋橋行
※伏見桃山駅まで約13分
(特急に乗車、丹波橋駅で普通または準急に乗り換え。最後尾の車両に乗ると改札口が近いです)
関連記事です!
月読神社 | 神功皇后ゆかりの「月延石」を祀る、安産守護のお社

京阪電車の次の駅は「中書島駅」は、伏見の酒蔵や寺田屋などもある、おすすめ観光スポットです。
※この記事の史実に関する記載は、御香宮神社パンプレット、駒札、Wikipedia等を参考に作成しました。
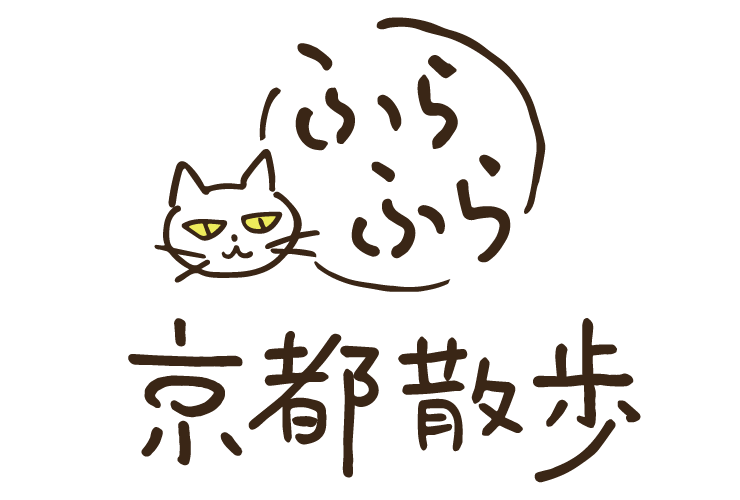
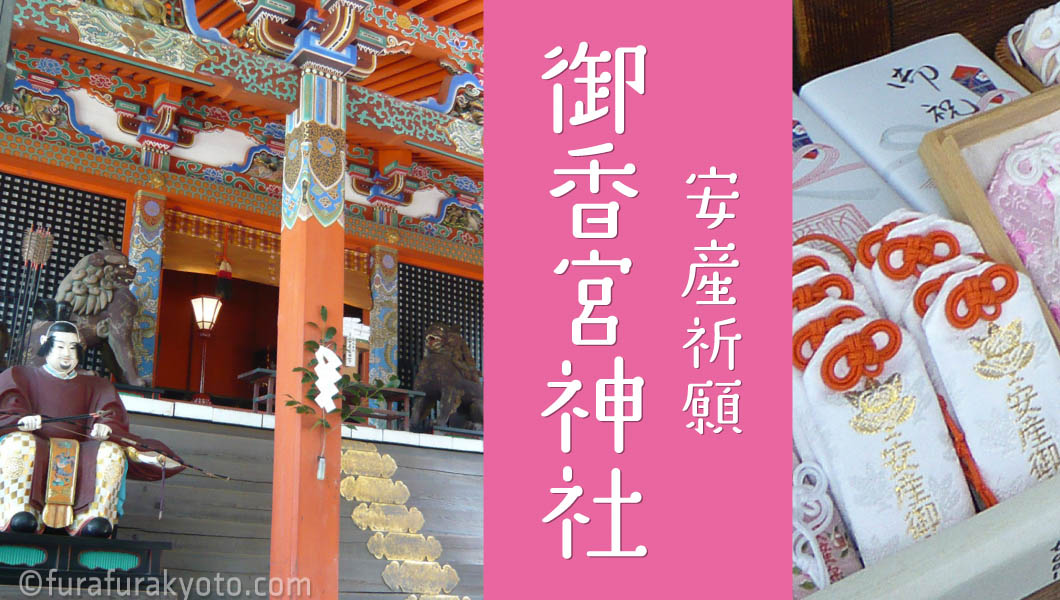
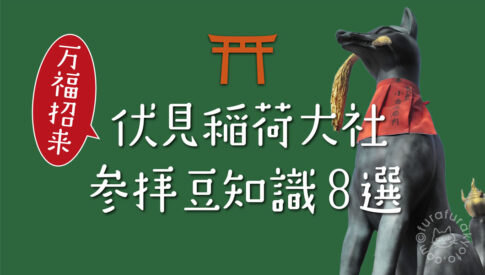












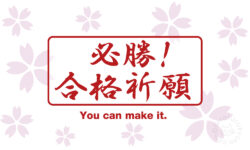

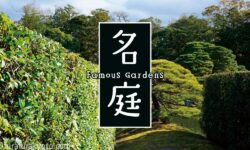



御香宮神社
所在地: 京都市伏見区御香宮門前町174
TEL. 075-611-0559
御祈祷受付 9:00~16:00 ※予約不要
御香宮神社 公式サイト