平野神社は平城京で創祀され、平安遷都の際に平野の地に遷座された由緒ある神社。本殿や拝殿などの建築物は江戸時代の再建です。
桜の名所としても有名で、毎年4月10日に桜花祭が行われ、桜花時期には桜茶屋(3月25日~4月20日のみ出店)も出店。夜桜も楽しめます。(日没~21時頃まで)
勝手にイチオシは可愛い置物おみくじ「リスのお告げ」。
由緒、御利益、見どころ、おすすめ参拝ルートをご紹介します。
タップできる|目次|
【1】平野神社の由緒
平野神社は、奈良時代末期に平城京で創祀された由緒ある神社です。延暦13年(794年)の平安遷都と同時に、この平野の地に鎮座されました。
・平城京から平安京へ
平野神社の御祭神・今木皇大神(いまきのすめおおかみ)は、延暦元年(782年)には平城京の田村後宮に祀られていたと推測されています。
平安遷都を行った桓武天皇の生母・高野新笠の祖神(桓武天皇外戚神)と伝わります。
延暦13年(794年)の平安遷都と同時に現在地に遷座。当時は、現在の京都御所(平安尺で1500m四方)とほぼ同じ広さがあったそうですが、現在は200m弱四方になりました。
平安時代の書物『延喜式』によれば、全国唯一の皇太子御親祭が定められた神社です。
出典:平野神社公式サイトより抄録
同式の「神祇官式・祝詞」には「皇大御神・皇大神」と称され、また「東宮坊式」には「神院」という宮中神と同様の扱いを受けています。全国でも数社に限られる、これらの尊称から宮中外の宮中神であったことがうかがえます。※宮中神:平安京の大内裏に祀られた神々
・天皇外戚の氏神
奈良時代末期に臣籍降下(皇族が源氏、平氏などの姓を賜り臣下になること)の制度が定まり、源氏・平氏・高階氏・大江氏・中原氏・清原氏・菅原氏・秋篠氏ほか天皇外戚*の氏神としても尊崇されました。
*外戚(がいせき)とは、天皇の母親または妃の一族のこと。
・平野神社の歩み
- 延暦13年(794年)第50代 桓武天皇の命により、田村後宮に祀られていた今木神・久度神・古開神の三神(総称・平野神)が平安遷都と同時にこの地に遷座。
- 平安時代中期に編纂された「延喜式」によると、全国で唯一、皇太子御親祭が定められ、皇城鎮護の神社二十二社の五位に列せられました。
- 天元4年(981年)第64代 円融天皇の行幸があり、以後も天皇の行幸が度々行われました。
- 寛和1年(985年)第65代 花山天皇により臨時勅祭が開かれ、天皇が境内に桜を手植して以来、桜の名所となりました。
- 中世以降は、応仁の乱(1467-1477)、天文元年(1532年)天文法華の乱により焼失し荒廃。
- 寛永年間(1624年~1644年)平氏嫡流の公卿 西洞院時慶の尽力によって再興が図られ、現在の本殿が造営されました。



平安遷都と同時に、平城京から遷座された由緒ある神様です。
【2】御祭神と御利益
平野神の御利益は、活力UP!
そして、御神紋は「桜」。桜は生命力を高める象徴とされています。
平野神と桜の霊験を拝受したら、ポジティブに頑張れそうですね!
・御祭神「平野神」
御祭神は4柱。本殿北の第一殿から順に1殿1柱ずつ祀られています。
主神である「今木神(いまきしん)」は「平野神」、尊称として「今木皇大神」と呼ばれます。
※平野神の呼称は、元々は主神の今木神のみを指していましたが、のちに祭神4神の総称として使用されるようになりました。
- 第一殿:今木皇大神(いまきのすめおおかみ)源気新生、活力生成の神
- 第二殿:久度大神(くどのおおかみ)竈の神、生活安泰の神
- 第三殿:古開大神(ふるあきのおおかみ)邪気を振り開く平安の神
- 第四殿:比売大神(ひめのおおかみ)生産力の神
今木神 平野神社に祭られる神。「今木」の「木」は「来」の当て字で、今あらたにきた人々が祭る神の意。もともと、大和国(奈良県)高市郡今木の地に住みついた渡来系の人々によって祭られていた神。光仁天皇の夫人高野新笠(百済系)の祖神とされたが、新笠の子の桓武天皇の代に至って現在の地に祭られ、のちに平氏の氏神となった。
出典:朝日日本歴史人物事典
・可愛いリスのおみくじ
御守など授与品の中でも可愛さで目立っているのが、おみくじ「リスのお告げ」です。
平野神からのお告げを、桜を抱いた可愛いリスから拝受しましょう!



平野神の御利益、活力UPは、諸願成就が望めるということですね^^
【3】平野神社のみどころ
見どころは本殿・拝殿。そして春は桜です。
・本殿
本殿は4殿2棟からなり、江戸時代前期の寛永年間(1624年~1644年)の再建。それぞれ今木神(第一殿)、久度神(第二殿)、古開神(第三殿)、比売神(第四殿)が祀られています。
第一殿と第二殿、第三殿と第四殿はそれぞれ空殿を挟んで連結する平野神社独特の形式で、「比翼春日造(ひよくかすがづくり)」、または社名から「平野造(ひらのづくり)」と称されます。国の重要文化財。


・拝殿
慶安3年(1650年)に東福門院(徳川家康の孫/後水尾天皇中宮)によって建立された文化的価値の高い建築物です(京都府指定文化財)。釘を使用せず接木の工法で作られ「接木の拝殿」とも呼ばれています。
2018年(平成30年)の台風第21号で全ての柱が折れて倒壊する被害に遭い、当時の工法や建築様式を後世に残すため分解調査しながら修復、2021年(令和3年)に完了ました。

・桜苑
平安時代の寛和元年(985年)に花山天皇が桜を手植えして以来の桜の名所です。貴族たちが桜の美しさを愛でた「観桜」の黎明期から桜と共にしています。

桜花祭(おうかさい)
桜花祭は、毎年4月10日に開催される京都の春の風物詩。約200名の時代行列が華やかに氏子地域を巡行します。
花山天皇が後胤繁栄(こういんはんえい)を祈るため平野神社へ行幸、臨時に行われた勅祭がはじまりと言われています。
多種多様な桜
現在、平野神社境内に植えられている桜は約60種約400本。平野神社原木の桜も多く、長期間(約1か月半)様々な種類の桜を楽しむことができます。
江戸時代になると庶民にも夜桜が開放され、「平野の夜桜」として京都を代表する花見の名所となりました。
珍しい種類の桜が多いのは、臣籍降下した氏族の氏神でもあったことから、蘇り、生産繁栄を願い、各公家が伝来の桜を奉納したからと伝えられています。
桜の種類と写真:公式サイト


桜が咲き誇る季節の平野神社は華やかで美しいです!
【4】平野神社 アクセス
最寄り駅
- バス停「衣笠校前」から北へ徒歩約3分。
- バス停「北野白梅町」から北へ徒歩約7分。
- 京福電鉄北野線「北野白梅町駅」北へ徒歩約7分。
・京都駅前バスターミナルから
- 京都駅前バスターミナルのりば案内
[B2のりば] 市バス50 立命館大学行に乗車「衣笠校前」下車。乗車時間:約37分
[B3のりば] 市バス250 京都水族館・金閣寺道行に乗車 「衣笠校前」下車。乗車時間:約39分 - TAXI 所要時間 約22分
・総距離 約7.1km タクシー料金検索
※料金・所要時間は実際とは異なる可能性があります。
・三条京阪前から
市バスのりば、京阪電車3番出口を出てすぐ
- [A1のりば]
市バス10 北野天満宮・御室・山越行に乗車「北野白梅町」下車。乗車時間:約31分
市バス15 円町・立命館大学行に乗車「衣笠校前」下車。乗車時間:約29分
市バス51 北野天満宮・立命館大学行に乗車「衣笠校前」下車。乗車時間:約31分

平野神社は北野天満宮の近くです。
・最寄りバス停からのルート
- 「衣笠高前」から ※地図のピンクのライン
「西の鳥居」の手前の道を右折「東の鳥居」→ 楼門→ 拝殿→ 本殿 の順序がおすすめ。
もちろん西の鳥居から入ってもOK。桜苑を経由して手水舎の横に出ます。 - 「北野天満宮前」から ※地図の水色のライン
北野天満宮を参拝してから行くコースもおすすめです。

春は桜に誘われて「西の鳥居」から入ってしまいます^^
【5】まとめ
桜が開花する季節は、混雑して本殿参拝にも行列ですが、 普段は静かに鎮座する神社です。シーズンオフにゆっくり参拝するのもいいと思います^^

※この記事の史実に関する記載は、平野神社公式サイト等を参考にしました。
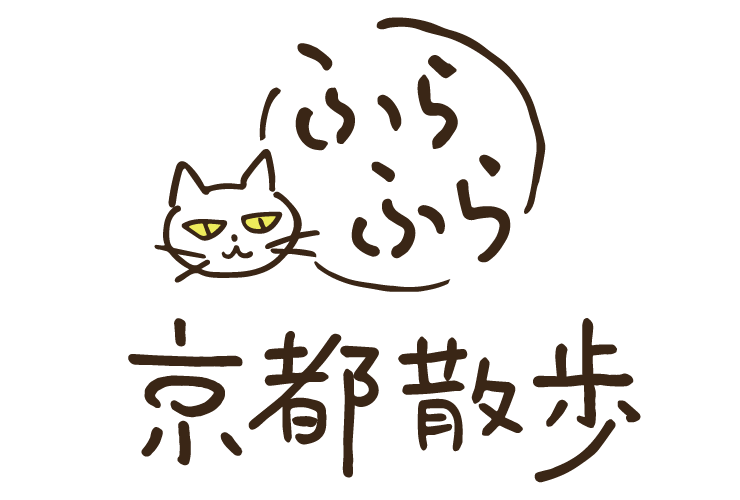





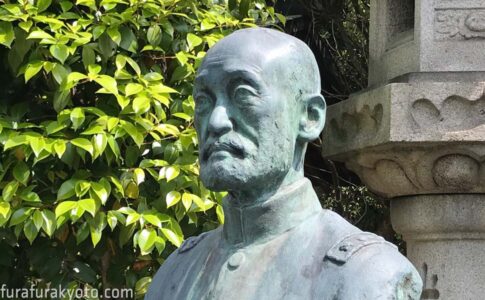








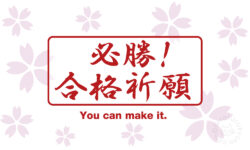

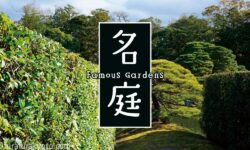



平野神社
所在地 京都市北区平野宮本町1番地
TEL.075-461-4450
※境内無料
社務所 9:00~17:00
平野神社公式サイト